
東京電力、福島第一原発の事故から10年経ちますが、今でも司法の場では国の責任の有無や原発の運転の是非が争われていて、最高裁判所で判断が確定した例は未だありません。いずれ最高裁判が結論を出すことになりますが、どのように審議を積み重ね、判断していく必要があるのか司法の役割や立場を考えていきます
3月2日時論公論~司法に求められていること -原発事故の判断
原発事故の判決の現状
解説委員:山形 晶(司法担当)
事故が起こる前、司法が原子力発電所の安全性に疑問を投げかけることはほとんどなかった
⇒原子力発電は極めて高度で専門性が高く、司法としては専門的能力を持っている規制当局の裁量を認めて判断することが尊重されていた
⇒司法は、事後的なチェックに徹するべきという抑制的な考え方が強かった
⇒1992年にあった原発事故で最高裁は「規制当局の判断に不合理な点があるか否か」で判断された
福島の事故後、司法では2013年に全国の裁判官や研究者が研究会を発足
「複雑困難訴訟」⇒原発訴訟とどう向き合うか?が議論された
⇒基本的な考え方(規制当局の判断に不合理な判断があるか否か)は生かすべきという意見が根強く、この時の議論や意見は色濃く残っているが、具体的な論点はより慎重により丁寧に検討すべきという意見も出ている
福島の事故後、実施されている裁判
◆福島の事故後、2つのタイプの裁判が実施されている
1:賠償を求める裁判(事故の責任を国や東京電力に賠償を求める裁判京電力は法律で賠償の義務を負っており、裁判では主に国の責任の是非が問われている【過去の規制の是非】)
2:運転停止・国の許可の取り消し【今の規制の是非】
◆1審判決:14件
⇒国に責任あり7件、責任なし7件
*刑事裁判では、東京電力の会長ら3人に無罪と判決を言い渡している
◆2審判決:3件
⇒国に責任あり2件、責任なし1件
【責任ありとなったのは2件とも、津波を予測し事故を防ぐことは可能と結論を下したため】
*事故の9年前、2002年に巨大な地震の可能性を示す長期的評価が公表されていた
⇒当局は科学的知見を十分に考慮していなかったと判断した
⇒未だ多く裁判が残っているが【過去の規制】に関しては、司法は当局に厳しい判決を下す傾向が強くなってきている
◆事故後、原子力規制委員会が設立され、規制基準が見直されている
【基準適合】・・・許可されたのは、全国の原発のおおよそ半数である、9原発にとどまる
⇒裁判所は規制委員会が合格させた判断を元にチェックしている
⇒裁判所は、規制委員会の規制基準や判断が妥当かチェックする役割に徹している
⇒当局の判断を尊重する考え方は踏襲させた
【事故前】運転停止・許可取り消し先は2件で、2件とも覆した
【事故後】7件許可されたが、そのうち5件覆した
⇒以前より国の規制に対して厳しい判断がされている
◆司法の判断への見解◆
・原発事故は人体や地域社会への影響が大きく、司法が踏み込んで判断するのは当然か?
・専門的知識がない素人の裁判官が原発を止めるのは疑問を投げかける意見もある、原発の再稼働を妨げる「司法リスク」でありエネルギー政策への介入ではないか?
裁判所に求められること!
どの程度のリスクなら許容されるか?
裁判所は規制当局の判断を前提に、問題ないか検討している
⇒裁判所は最後のチェック機能として、重大な事故を起こさないために【安全装置】としての役割が期待されている
⇒地震・津波・火山の噴火による原子力発電所への影響を理解することが重要
そのために、双方からプレゼンテーションをしてもらったり、専門家を呼んで質問し理解を深める
⇒裁判官は社会通念を理解する必要がある

司法は、重大な事故を起こさないための最後の砦です
司法がどのような判断を下していくのか、丁寧に審議を積み重ね最終判断(最高判断)をどのようにするのか誰もが納得できる判断を示すことができるように、必要な努力をしていくことが司法にも求められています




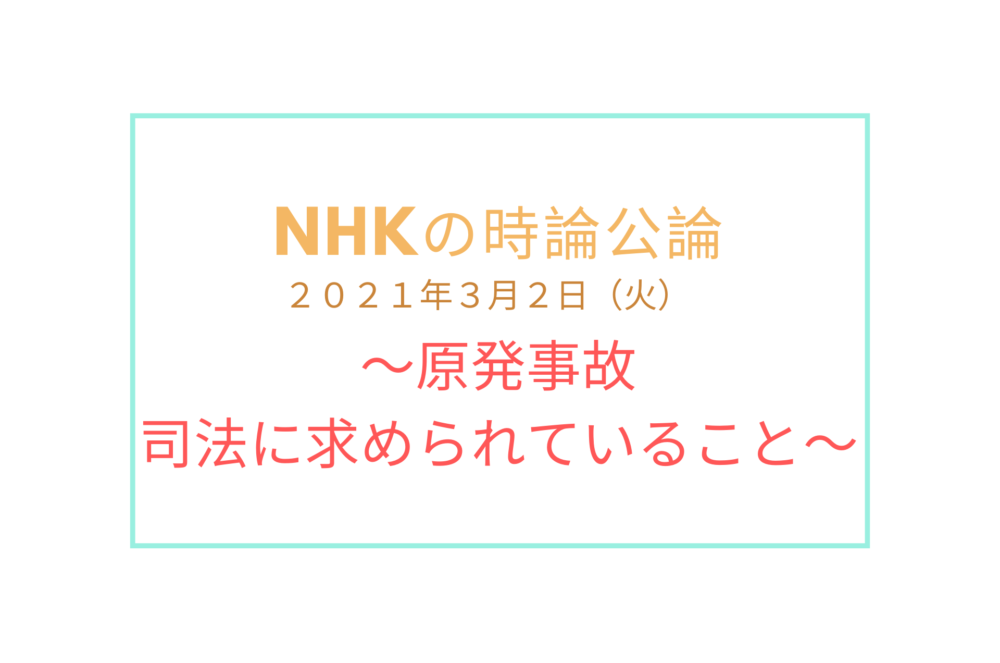


コメント