
来月4月より新たな70歳就業法が施行され、70歳まで希望する人は引き続き働けるように企業へ努力義務が課せられます。サラリーマンにとって、一生涯現役で働く社会が現実になってきました。今回の就業法改定によって、社会はどう変わるのか考えていきます。
3月15日の時論公論~70歳まで雇用の努力義務:新たな働き方
なぜ70歳就業法が施行されるのか、なぜ国は70歳まで働かせたいのか
⇒人手不足への対応と社会保障を維持するため
・現在、若い人2人で高齢者1人を支えている
・今後2040年には、1.5人で高齢者1人を支えなければならず、2065年には1.3人で1人を支える必要がある
⇒若い人がひとりで二人分の税金を納めなければいけない状況になる
⇒高齢者には今後、できるだけ長く働いてもらう必要がある
働き手側の気持ちはどうなのか
・早く引退して悠々自適な生活をしたいっという不満に思う意見もあるが
今回の法律は働きたくない人を無理に働かせる制度ではなく、働きたい人に企業が働けるように雇用を努力する義務が課せられたもの
◇実際の希望状況(内閣府のアンケート:平成26年実施)
「(60歳以上で働いている人に)いつまで働きたいか」
⇒少なくとも70歳ぐらいまで働きたいと答えた人が約8割いた。
「60代で働く理由」:経済上の理由と答えた人が6割いた
*働かざるおえない事情がある人に向けた制度である
そのため、「高年齢者雇用安定法」が改正され、70歳就業法が2021年4月から施行される
『希望する人が、70歳まで働けるようすべての企業に努力義務を課す』
| 現在 | 義務(65歳まで) ①②③から企業が選択 | 形態 | 4月から | 努力義務(65歳~70歳) ①②③④⑤から選択 |
| ① | 定年引上げ:65歳まで | 雇用 契約 | ① | 定年引上げ:70歳まで |
| ② | 定年の廃止 | 雇用 契約 | ② | 定年の廃止 |
| ③ | 再雇用:65歳まで | 雇用 契約 | ③ | 再雇用:70歳まで |
| 非 雇用 | ④ | 業務委託契約(企業主、フリーとして業務を請け負う) | ||
| 非 雇用 | ⑤ | 社会貢献事業(有償ボランティア) |
*65歳までは雇用のみだが、70歳以降は雇用以外での働き方が選べるような制度になった
⇒健康や働く意欲、体力に応じた選択ができるような制度となった(多様な働き方)
◆非雇用で働く際の注意点◆
・労働法の保護を受けることができない(労働時間の規制や、最低賃金の取り決めがない)
・社会保険料の事業主負担なし
⇒偽装請負の恐れがある(実際には雇用契約時と同様の働き方をしているなど)
そのため、企業が非雇用制度を利用する場合には組合の許可が必要
◆問題点◆
①会社が対象者を限定する基準を制定できること
⇒会社側が引き続き働ける人と働けない人を決めることができる
国のガイドラインでは、労使の協議が必要で具体的な就業規則での取り決めが必要とはしている
(例えば、過去何年間の人事考課(出勤率など)がいくつ以上あった人など)
②働き手が高齢者になればなるほど、労災になる人が増えること
2019年の段階で、労災の死傷者の内、60代以上が26%を超え4分の1を占めている
さらに高齢まで働けるようになればさらに増えると考えられる⇒高齢者が安心して働ける環境が急務
*高齢になっても、働きがいをもって生涯現役として生き生きと働ける環境づくりが必要

今回の70歳就業法はあくまでも、努力義務でできていない企業に対して罰則はありません。ただ今後の人口減少に伴って、長く働くことが求められるのは間違いありません。仕事が生きがいになって、長く働きたいとみんなが思えるような環境になればいいのかもしれません。






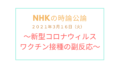
コメント