
2020東京オリンピック・パラリンピックの開催予定日まであと半年。コロナの影響により2021年に延長され、今もなお感染拡大で開催を不安視されるなか森会長が辞任することになりました
問題視された女性蔑視、社会や世界からの批判が拡大され続けています
この問題を通し日本は日本社会への課題を受け止め環境を変えていくことができるのでしょうか
2月12日時論公論~女性蔑視への問題と課題
解説委員:小澤 正修(スポーツ担当)
専門解説委員:飯野 奈津子(人権・共生担当)
2月12日本日、組織委員会は理事や評議委員会を集め森会長が自ら辞任することを発表した
森会長の女性蔑視と取れる発言は今月2月3日のことだった
◆今月2月3日:JOC(日本オリンピック委員会)の評議委員会にて◆
評議委員会で、JOC女性理事の割合を40%以上にする目標が定められた
この目標の後に、JOCの名誉会長である森会長が挨拶をする際に女性蔑視ととれる発言をした
女性がたくさん入っている理事会は時間がかかる
◆翌日2月4日:「不適切だった」と撤回し謝罪
⇒国内外からの批判が収まらなかった
◆森会長の貢献と批判への対応◆
*総理大臣を経験し豊富な人脈を持つ、森会長の手腕と批判との狭間による厳しい対応が迫られた
オリンピック・パラリンピックの大規模イベント開催には、政府や財界、スポーツ界などと複雑な調整が必要となってくる
森会長は、昨年2020年には、コロナの影響で感染拡大を懸念し過去に例のない史上初の大会延期や経費削減のため他の県にある既存の施設への変更などの対応した
⇒大会関係者の多くが森会長だからこそ難しい課題が解消できたと指摘している
大会まで半年を切りながら依然として感染状況を見通せず、具体的なコロナ対策や観戦者をどうするか課題はまだまだ多い、後任の新しい人が森会長の代わりを担うのは困難ではないかと見られてもいた
しかしながら、一連の騒動で大会を支えるボランティアや聖火ランナーの辞退が相次ぎ、スポンサーからの苦言もあり、IOCも2月9日に「完全に不適切」と改めて声明を出した
森会長は、開催するためには辞任しか前に進めないと判断し2月12日に辞任することを表明した
◆人の振る舞いを性別で判断し決めつけること
⇒偏見や差別につながる
・今回の場合、女性は競争意識が強く話が長いと決めつけたことが問題
・社会の中でも、家事や育児で責任ある仕事は難しいという決めつけが壁になっている
◆性差別への感度の鈍さと事なかれ主義の組織環境
⇒誰もその場で発言を注意する人がおらず、発言の撤回だけで謝罪せずに簡単に解決したと見なしたこと
・欧州各国の在日大使のTwitterでのメッセージ(キーワード):#Dontbesilent
“沈黙は肯定していることと変わらない、だから沈黙しないで”っと日本社会へメッセージを送っている
◆意思決定の際に自由で活発的な議論を封じ込めていないか
⇒森会長の「組織委員会にも女性はいるが、場をわきまえている」という発言が、女性への発言を否定し時間をかけた自由な議論をすること自体も否定していると批判された
⇒委縮せずに、意見を出し合って共に考えられる社会を作っていくことが重要である
*Twitterで「#わきまえない女」というキーワードが広まっている
⇒性別に限らず属性に固執せず(決めつけず)に、判断しないようにすること
オリンピック・パラリンピック開催実現へ求められること

組織委員会には日本国内や海外からの信頼や共感を取り戻すが求められます
今回の批判が拡大した原因は、立場上、東京大会で最も遵守しなければいけない理念に反していると判断されたからです
◆オリンピック憲章の根本原則◆
人種・性別・性的指向・宗教などあらゆる差別を認めないと明記
◆東京大会コンセプト
多様性と調和を掲げている
東京五輪では、女性選手の割合も48.8%となり男女ほぼ同数になる予定

この理念の存在こそが大会の最大の特徴であり、理念に賛同していた人たちは落胆し、コロナ感染で開催自体に反対していた人たちにはさらに反感を強めてしまいました
求められる社会の変革
日本は男女平等の後進国です
2020年に世界経済フォーラムで発表された世界の男女平等度ランキングで、
1位がアイスランド、2位がノルウェー、3位がフィンランドでしたが、
163カ国の中で、日本は121位でした
◆日本の目指すべき社会である女性差別のない多様性を重んじる社会を作るために重要なこと
①意思決定の場に女性を増やす仕組みづくりをする
②委縮せずに意見が出せる環境を整備する
③属性の基づく決めつけがないか自問すること

今回の女性蔑視の問題をきっかけにして、大会時だけでなく
日本全体で多様性の価値観を認め合い社会が変わるきっかけになってほしいです




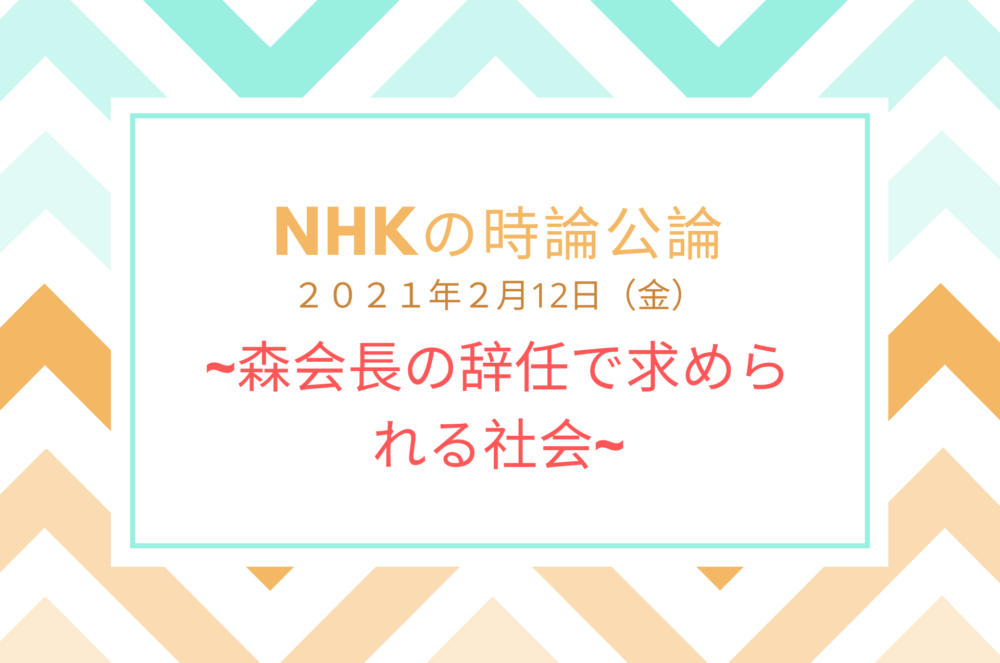
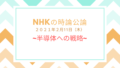

コメント