
東日本大震災から10年、復興のこれからはどうなるのか考えていきます
3月11日の時論公論~これからも続く復興をどう進めていくのか
2万2千人以上の被災者を出した東日本大震災はこれからどう進めていくべきか
この10年、国は30兆円以上を投じ防潮堤や災害公営住宅、インフラ整備を進めてきた
NHKのアンケートで、今の復興は思い描いていたより悪いと答えた人が多かった
復興を実感できない理由は、10年が経ち復興の様々なギャップが現地に広がっている
・インフラの整備はできたが、にぎわいが街に戻らない
・新居での新生活は始まったが、地域での交流が減り高齢者の孤立化が加速した
・人口が増えた地域と人口の流出や高齢化が加速した地域が分かれている
分野や地域、個人による差が目立ってきている
被災地を南北に走る復興道路によって輸送や移動はらくになったが、かさ上げ地では利用が決まらない状態、空き地が広がっている
・地権者や相続人の確認、住民の合意を得て移転先を決めるなど課題が多く長期間で調整が必要だった、そのため元々は地元に残って市内で移転を希望していた人でも若い世代を中心に財務状況等に余裕がある人から市外に移り住んでしまった
特に復興が遅れているのは福島第一原発事故による対応
・福島第一原発事故の影響により、今も3万6千人が避難している
⇒避難指示が解除された地域の住民帰還率は、たったの21%しかない
地元で再開した事業者は、40%で働くところの確保も大きな課題となっている
原発に近い福島県の浪江町では、原発事故前に24社あった水産加工業者が昨年2020年に9年ぶりに再会させた1社しかない。その1社も再開することに躊躇いはあったが周りからの強い要請を受けてもう一度再開させることに決めていた。風評被害を心配はしていたが、常磐ものと呼ばれる魚の評価は変わっていなかった。
・国がロボット、再生可能エネルギー、廃炉、航空、宇宙など先端産業を集積させる
・地元事業者の参入を促し、雇用の拡大につなげられるか検討されている
⇒官民合同チームの専門家による事業支援で事業再開を呼び掛けたり、起業を支援している
国はその他にも、原発被災地への移住を促す政策で移住では最大200万円の支給と起業する場合には400万円を支給することにし最大で600万円を支給することにしている。
住民が戻らないなら他の人を呼び込めばいいとするだけでなく、被災者への支援も怠ってはいけない
・避難者の全体像を把握することが大事【民間協力することが大事】
・その上で、支援が届いているのか検証を実施する
⇒収入の不安定さや相談する人がいないなど困窮・孤立化が被災地では進んでいる
・困窮者を救済する制度が必要だと国会で検討されている段階
◆原発事故賠償および期間できない理由◆
・事故賠償は、「国指針・東電基準を超え自主避難を含む避難者に賠償を命じる」判決が相次ぐ
⇒基準にとらわれない支援のあり方を検証する必要があるとなった
・なぜ帰還できないのか
⇒「山林や草地の汚染が残っていると思える」46%
約半数の人がまだ安心して帰還できる状況になっていないと判断⇒除染・解除の見通しを示す必要がある
⇒新たな街のあり方を検討している段階
*検討:村と避難先の二重住民票
*準市民制度として、ふるさとに住民票を残し避難先で市民に準ずる資格
⇒ふるさととの繋がりを公的に保つ仕組みづくり(こころの拠り所にもなるのではないか)
⇒復興の需要が減り、自主的な街の復興がされなくなるのではないか

東日本大震災から10年が経ち、震災前の街を知らない世代が増えてきています。
復興されずに見捨てられた街とならないために、また街のにぎわいを取り戻し楽しく人が集まる街となるように、国の支援だけでなく民間事業も協力しあい未来ある街づくりをより早く復興計画を進めていってほしいです。




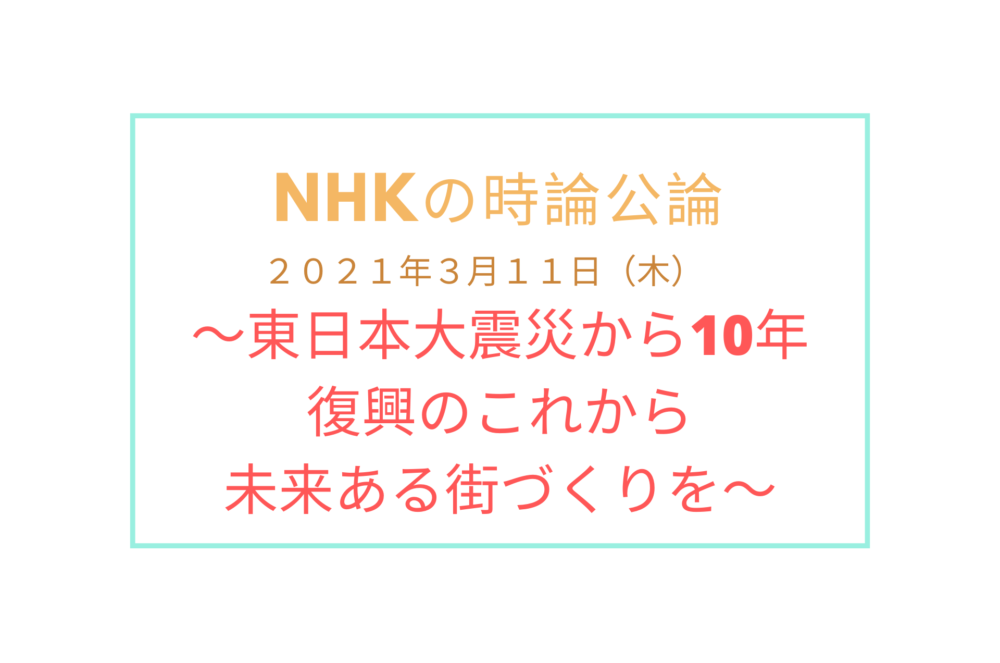

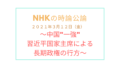
コメント